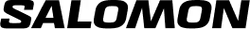太田安彦(一般社団法人マウントフジトレイルクラブ代表理事)
田代広久(富士吉田市案内組合 組合長)
池敏子(富士山ガイド)
北口本宮冨士浅間神社から山頂までを結ぶ吉田口登山道は、富士山の登山道のうち、山麓から山頂まで歩いてアクセスできる唯一のルートです。かつては“富士みち”として親しまれ、富士講の行者による登拝がさかんに行われていましたが、1964年に富士スバルラインが開通してスバルライン五合目が設置されると、五合目以下の利用者が激減。登山道は一気に荒廃していきました。

吉田口登山道には富士山信仰の歴史をいまに伝える神社や小屋跡、石造物が残されていますが、その多くが老朽化しています。富士みちをどう活用し、歴史的価値や楽しみ方を伝えていくのか。こうした現状や課題を、登山道にまつわる歴史を学びながら、活用を考えようというワークショップが、サロモンを含めたアメアスポーツジャパンのスタッフとその関係者に向けて実施されました。
ここではワークショップの内容をお伝えするとともに、富士山と富士登山にまつわる文化や活動をサポートするサロモンスタッフが、吉田口登山道が抱える課題に対してどんな思いをいただいたのか、リアルな声もご紹介します。


開山直前の週末に行われた「富士山登山道整備ワークショップ」。当日の朝、スタート地点となった中ノ茶屋前には、東京から参加したサロモンのスタッフを中心に、アメアスポーツジャパンおよびその関係者30名と、それを迎える富士吉田市職員、そしてワークショップを引率するガイドが集合しました。
プログラムは「ユネスコ世界文化遺産の構成要素である山域の信仰遺跡群と文化財を多くの人に見てほしい」という堀内茂・富士吉田市長の挨拶でスタート。続いて登場したショーン・ヒリアー・アメアスポーツジャパン代表取締役社長は「環境、スポーツ、富士山の自然……大事なことに思いを馳せながら歩いてみましょう」と、ワークショップでの心構えを説きました。


中ノ茶屋でのオリエンテーション後、参加者はバスにのって細尾野林道入り口へ。ここから本日のガイドを務める太田安彦さん(一般社団法人マウントフジトレイルクラブ代表理事)と田代広久さん(富士吉田市案内組合 組合長)、池敏子さん(富士山ガイド)の案内のもと、三合目から一合目直下の馬返しまでを歩きます。三合目に至る細尾野林道は、本線と比べるとハイカーやトレイルランナーの姿もぐっと少なく、ヘビイチゴやヤマツツジなどこの時期に花咲く植物を眺めながら静かな山歩きを楽しめます。三合目の手前に現れたのが「女人天上(にょにんてんじょう)」という遥拝場。富士山が女人禁制だった時代、女性たちはここから富士山を拝んだといいます。ここで太田さんから、富士山信仰についての解説が行われました。

「富士山信仰は古代、噴火を繰り返す富士山そのものを神格化する自然崇拝から生まれました。当時は遠くから眺め、畏怖する対象だったようです。平安時代になると日本古来の山岳信仰と密教・道教が結びついて修験道が盛んになり、行者による登拝が行われるようになりました。15〜16世紀になると登拝が庶民にまで広まり、富士講の開祖・長谷川角行とその弟子、食行身禄(じきぎょうみろく)によって一気に大衆化。富士吉田の街には御師町(おしまち)が開かれ、日本全国から信者が押し寄せるようになりました。そこから現代のレジャー登山へと開かれていくのです」

富士山とご来光を同時に見渡せるスポットですが、登山道本線から外れていることもあり、ここの存在はほとんど知られていません。けれども、女性の入山が禁じられていた山岳信仰の当時の姿や、富士講が説いた男女平等を実現するために男装で登った女性信者のエピソードが残る「女人天上」は、富士山信仰を伝えるうえで欠かせないスポット。富士山の吉田口登山道のハイライトの一つとしてここをどう活用するか、今後の課題の一つとなっています。

「女人天上」を経て三合目(標高1840m)の、通称「三軒茶屋」へ。富士五湖を一望するロケーションで、江戸時代には「見晴茶屋」と「はちみつ屋」という小屋があり、お茶を点てて登拝者をもてなしていました。ここに残されている廃屋は、かつての「はちみつ屋」跡。残置された廃材・廃屋は登山道の景観を損ねますが、国立公園内に位置することもあってさまざまな規制の対象となっており、再建や撤去が難しいのだといいます。

三合目からさらに下り、二合目(標高1700m)の富士御室浅間神社跡へ。河口湖の南岸にある富士御室浅間神社の本宮で、富士山で最古の創建と伝えられます。戦国時代には武田信玄が勝利を祈願したという由緒ある神社ですが、こちらも登山道の荒廃とともに参拝や維持がなされなくなり、倒壊してしまいました。その先、一合目にある鈴原社も建物の一部が損傷しています。この周辺には富士講に関する石碑が残されていますが、地震によって倒壊したり、一部が欠損していたり。こちらも速やかな対策が求められています。

「10年前に富士吉田市が建造物調査を行い、それを受けて一部の建造物の建材の撤去を行いましたが、あれから時間が経って残された建物の損傷も進んでいます。費用の問題に加え、ユネスコ世界文化遺産に指定されていることからさまざまな制限を受け、今後の事業計画を立てづらいという問題があります。撤去するのか、保全して活用するのか、活用するならどう使うのか。ぜひみんなで考えていきたいですね」(太田さん)



その先の大文司屋を経て馬返しから再び中ノ茶屋に戻り、トレイルの振り返りを行いました。グループに分かれ、吉田口登山道で見つけた課題を洗い出し、ディスカッションを行います。
「初めて吉田口登山道にまつわるストーリーを耳にし、信仰の道、文化の道としての魅力を感じた。とはいえ、こうしたストーリーを知る人が少ないのは残念。各スポットを紹介する音声ガイドに飛べるQRコードが用意されているものの、その存在も知られていない」
「中ノ茶屋には今年からスターリンクも導入されたのだから、これを活用してデジタルコンテンツを作成できるのでは?」
「富士吉田の街と登山道を結びつける仕掛けが必要だと思う。トレイルランナーは多く見かけたので、ランナーが魅力に感じる演出を、富士吉田の街にも作るといい」
「御師町と五合目以下のつながりを楽しめる、デジタルガイドツアーのような仕掛けを作っていけないか」
「音声ガイドの存在をアピールするため、富士講とゆかりのある場所でデジタルガイドツアーを開催するのはどうだろう。都内にも富士講に関する史跡が点在するというから、それをめぐるロゲイニングイベントを行い、富士講と富士みちの認知を高めてみては?」

このように、さまざまなアイデアの交換が行われました。こうしたアイデアをもとに今後、吉田口登山道から新たな試みが生まれてくるかもしれません。開山を前に本格始動した「Mt.FUJI Re-Style Project」にご期待ください。