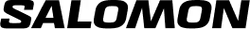標高3100m。富士山の吉田ルート八合目には、長年登山者を見守り続ける救護所がある。
「富士山八合目富士吉田救護所」。そこに20年近くボランティアで通い続ける岩瀬史明医師に密着。標高3000mを超える高所という特殊な環境による体調不良者が続出する、富士山における医療の最後の砦の重要性を知る。
医師でありランナー
八合目まで駆け上がる
まだ空気がいくぶん涼しい、真夏の早朝6時。
富士山の登山口である中の茶屋の前を2人のランナーが駆け抜けていく。
先頭をいくのは、山梨県立中央病院に勤める岩瀬史明医師。

向かう先は「富士山八合目富士吉田救護所」だ。八合目に位置する山小屋、太子館に併設された救護所で、岩瀬医師をはじめとした地元や県内外の医療従事者たちが、24時間体制で診療や応急処置を無償でおこなっている。3000m付近から高山病の症状を訴える人が多数いたことから、2002年に開設。開山期間中の7月上旬から9月上旬にかけて毎年開設され、年に300〜400人の受診者を受け入れている。
岩瀬医師が救護所ボランティアをはじめてから、すでに18年になる。

サロモンのギアで身を固めている。走ることが趣味なのだ。通常だったら車で五合目まで上がって、その後はクローラー(運搬車)で八合目まで上がるのだが、岩瀬医師は毎年走って上がっている。走れるドクターなのだ。
フルマラソンの自己ベストは2時間20分台という実力。高低差3000mを一気に駆け上がる富士登山競走にも出場していて、過去には年代別1位など輝かしい成績をおさめている。毎年、救護所まで走って上がるのはトレーニングの意味もあるが、富士山の五合目までの道のりがとても好きだからだという。
「良い森なんですよ。五合目から先とはぜんぜん違う風景なので、ぜひ1度歩いてみて欲しい場所です」

高所環境が引き起こす高山病が
体調不良の約半分を占める
9時には八合目まで上がってしまうという岩瀬医師に遅れること数時間。救護所に到着すると、岩瀬医師の姿がない。捻挫をした患者さんを急遽六合目までクローラーで下ろして、再び八合目まで戻ってくるという。

救護所には他のボランティアスタッフの方々もいて、シーズン中は20ほどのチームが2泊3日交代で常駐している。救護所がある太子館前のベンチで待っていると、岩瀬医師が戻ってきた。今日だけですでに相当な移動距離だが「良い高所順応になりました」と、ピンピンしている。


登山者が次々と救護所前を通り過ぎていく。それにしても、いろんな人がいる。いかにも山に慣れていそうな人から、今回が山登り自体はじめてだという人まで、国籍もさまざまだ。
一時期は宿泊せずに夜通し歩く弾丸登山が問題になっていたが、昨年から山梨県側では五合目にゲートを設置。14:00~翌3:00まで通行止めにするなどの規制をおこなっている。
「一気に上がってくると、体が環境に対応できず高山病になるリスクが激増しますから、この規制はかなり効果があると思います。体調不良の統計で言っても4〜5割くらいの方が高山病です。その予防のためにも、休みながらゆっくり登ってくること、そして水分をこまめに補給することを心がけて欲しいです」


普段は山梨県立中央病院の救急救命センターに勤めていて、重篤な救急患者を受け入れている岩瀬医師。とうぜん普段の職場と、3100mという高所に位置する救護所ではだいぶ勝手が違う。
「富士山に登ってくるぐらいなので、基本は健康な人たちです。だから具合が悪くなったら下山を促すのが主な役割だと思っています。ただ、その判断というのはなかなか難しい。自力で歩いて下りられるのか、クローラーに乗せる必要があるほど切迫しているのか。だからガイドさんなどとも相談しながら、適切な判断をしていく必要があります」
当然、医療器具なども必要最低限だから現場での処置というよりは、安全に下ろすというのが重要になってくるのだ。


便利な移動手段がない中
“走れる”というメリット
しばらくすると岩瀬医師がトレイルラン用パックに、ファーストエイドキットを入れて背負う。山頂まで体調を崩している登山者がいないかパトロールに行くという。普通の足だと頂上まで行くだけでも3、4時間かかるが、岩瀬医師は1時間半ほどで戻ってくるという。

「山頂直下は体調を崩したり、怪我をする人がとくに多いので、毎日1度は見回るようにしています。パトロールだけじゃなく、現場に急行しないといけないこともあるんです。どこかの山小屋で体調を崩した人が出たという連絡が来たら、往診のような形で向かいます」
そうした現場に赴くためには、やはり普段から鍛え抜かれた脚力がものを言う。小屋からすぐ上の岩場をぐいぐい登って、あっという間に見えなくなる。


救護所から少し登った場所。見上げるとさきほどから日差しが強い。富士山の五合目以降は、樹木がほとんど生えていないから日陰がほとんどないのだ。
「風雨をしのげる場所も小屋周辺に限られるので、急な大雨などが降ったら低体温症の危険も出てくる」という、先ほど聞いた岩瀬医師の注意喚起の言葉にも繋がる。
目まぐるしく動いていく雲を眺めながら待つこと1時間。砂埃を上げながら、岩瀬医師が戻ってきた。
「いま救護所に患者さんが来ているという連絡があったので、ちょっと急いで下りちゃいます」という言葉を残し、そのまま駆け下りていく。

昼夜を問わず訪れる患者たち
山岳医療に休息はない
まっすぐ歩行できなくなったという症状の患者さんの診察を終えた岩瀬医師に、最近の登山者の傾向を伺ってみた。
「海外もそうですが国内でも遠方から来る人が多いように感じます。だからどうしてもスケジュール的にタイトになりがちです。つまり、登る前にすでに疲れているから、予期せぬ怪我や体調不良に繋がっているケースが多い。できれば体をゆっくり休めてから登山に臨んで欲しいですね。あとは装備関係。比較的登りやすいとは言え、標高は日本一ですから天候が荒れれば一気に気温も下がります。しっかりとしたレインウェアや防寒具、乾きやすいインナーなど登山に適したウェアや道具の準備がとても大切です」


日が傾くと同時に、救護所を訪れる人が増えてくる。長時間の登山を終え、ふっと気が抜けた時に症状がでる人も多いようだ。症状でいうと、高山病、熱射病、捻挫などが主だという。
ただ、ごく稀に重篤な患者さんも出ることもある。
「毎年、何人かは突然亡くなってしまう方もいます。今年も僕の前に入っていた班の時に、心肺停止になった登山者もいたようです。八合目あたりでそういう重篤な症状が出てしまうと、麓の病院まで下ろすのに、どんなに急いでも2時間以上はかかってしまいます。だから最初の心肺蘇生が非常に重要になってくる厳しい環境なんです。体調管理をしっかりしてから登ってきて欲しいというのが、現場の願いです」
すでに日没を過ぎているが、発熱したという人たちが救護所の前に列を作っている。結局この日、救護所の灯りが消えることはなかった。


翌日山頂まで足を伸ばす。美しい朝日に照らされた登りの道中で振り返ると霧に包まれた山中湖。はるか遠くには駿河湾まで望める。3776mという高峰ながら、独立峰なので視界を遮るものがない。他の3000m級に登ったとしても、この抜け感は得られない。これは確かに一生に一度は見ておきたい、オンリーワンの景色だ。


帰路、まもなく五合目に着くというところで、見覚えのあるウェアのランナーが登ってくる。まさかの岩瀬医師との再会だ。背中にはなんとAED(自動体外式除細動器)を背負っている。早朝、体調を崩した登山者を下ろして、いまは八合目にもどる途中なのだという。見ていた1日半の間だけでも、富士山を軽く2往復している。山に登る者として、岩瀬医師のような人たちがいるおかげで、安全に登れていることを忘れてはいけない。頭が下がる思いで、駆け上がっていく岩瀬医師の背中を見送った。


統括部長 岩瀬史明 医師
山梨県出身。山梨県唯一の救急救命センターにて統括部長を務める。2012年に山梨県でドクターヘリが導入された当初からの中心メンバーでもあり、2012年12月の中央道・笹子トンネル崩落事故にも出動。「富士山八合目富士吉田救護所」にボランティアとして2007年から参加。それ以降、毎年救護所に詰めている。趣味はマラソン、トレイルランニングで、市民ランナーとしてはトップクラスの成績を残している。

太田安彦(一般社団法人マウントフジトレイルクラブ代表理事)
田代広久(富士吉田市案内組合 組合長)
池敏子(富士山ガイド)
北口本宮冨士浅間神社から山頂までを結ぶ吉田口登山道は、富士山の登山道のうち、山麓から山頂まで歩いてアクセスできる唯一のルートです。かつては“富士みち”として親しまれ、富士講の行者による登拝がさかんに行われていましたが、1964年に富士スバルラインが開通してスバルライン五合目が設置されると、五合目以下の利用者が激減。登山道は一気に荒廃していきました。

吉田口登山道には富士山信仰の歴史をいまに伝える神社や小屋跡、石造物が残されていますが、その多くが老朽化しています。富士みちをどう活用し、歴史的価値や楽しみ方を伝えていくのか。こうした現状や課題を、登山道にまつわる歴史を学びながら、活用を考えようというワークショップが、サロモンを含めたアメアスポーツジャパンのスタッフとその関係者に向けて実施されました。
ここではワークショップの内容をお伝えするとともに、富士山と富士登山にまつわる文化や活動をサポートするサロモンスタッフが、吉田口登山道が抱える課題に対してどんな思いをいただいたのか、リアルな声もご紹介します。


開山直前の週末に行われた「富士山登山道整備ワークショップ」。当日の朝、スタート地点となった中ノ茶屋前には、東京から参加したサロモンのスタッフを中心に、アメアスポーツジャパンおよびその関係者30名と、それを迎える富士吉田市職員、そしてワークショップを引率するガイドが集合しました。
プログラムは「ユネスコ世界文化遺産の構成要素である山域の信仰遺跡群と文化財を多くの人に見てほしい」という堀内茂・富士吉田市長の挨拶でスタート。続いて登場したショーン・ヒリアー・アメアスポーツジャパン代表取締役社長は「環境、スポーツ、富士山の自然……大事なことに思いを馳せながら歩いてみましょう」と、ワークショップでの心構えを説きました。


中ノ茶屋でのオリエンテーション後、参加者はバスにのって細尾野林道入り口へ。ここから本日のガイドを務める太田安彦さん(一般社団法人マウントフジトレイルクラブ代表理事)と田代広久さん(富士吉田市案内組合 組合長)、池敏子さん(富士山ガイド)の案内のもと、三合目から一合目直下の馬返しまでを歩きます。三合目に至る細尾野林道は、本線と比べるとハイカーやトレイルランナーの姿もぐっと少なく、ヘビイチゴやヤマツツジなどこの時期に花咲く植物を眺めながら静かな山歩きを楽しめます。三合目の手前に現れたのが「女人天上(にょにんてんじょう)」という遥拝場。富士山が女人禁制だった時代、女性たちはここから富士山を拝んだといいます。ここで太田さんから、富士山信仰についての解説が行われました。

「富士山信仰は古代、噴火を繰り返す富士山そのものを神格化する自然崇拝から生まれました。当時は遠くから眺め、畏怖する対象だったようです。平安時代になると日本古来の山岳信仰と密教・道教が結びついて修験道が盛んになり、行者による登拝が行われるようになりました。15〜16世紀になると登拝が庶民にまで広まり、富士講の開祖・長谷川角行とその弟子、食行身禄(じきぎょうみろく)によって一気に大衆化。富士吉田の街には御師町(おしまち)が開かれ、日本全国から信者が押し寄せるようになりました。そこから現代のレジャー登山へと開かれていくのです」

富士山とご来光を同時に見渡せるスポットですが、登山道本線から外れていることもあり、ここの存在はほとんど知られていません。けれども、女性の入山が禁じられていた山岳信仰の当時の姿や、富士講が説いた男女平等を実現するために男装で登った女性信者のエピソードが残る「女人天上」は、富士山信仰を伝えるうえで欠かせないスポット。富士山の吉田口登山道のハイライトの一つとしてここをどう活用するか、今後の課題の一つとなっています。

「女人天上」を経て三合目(標高1840m)の、通称「三軒茶屋」へ。富士五湖を一望するロケーションで、江戸時代には「見晴茶屋」と「はちみつ屋」という小屋があり、お茶を点てて登拝者をもてなしていました。ここに残されている廃屋は、かつての「はちみつ屋」跡。残置された廃材・廃屋は登山道の景観を損ねますが、国立公園内に位置することもあってさまざまな規制の対象となっており、再建や撤去が難しいのだといいます。

三合目からさらに下り、二合目(標高1700m)の富士御室浅間神社跡へ。河口湖の南岸にある富士御室浅間神社の本宮で、富士山で最古の創建と伝えられます。戦国時代には武田信玄が勝利を祈願したという由緒ある神社ですが、こちらも登山道の荒廃とともに参拝や維持がなされなくなり、倒壊してしまいました。その先、一合目にある鈴原社も建物の一部が損傷しています。この周辺には富士講に関する石碑が残されていますが、地震によって倒壊したり、一部が欠損していたり。こちらも速やかな対策が求められています。

「10年前に富士吉田市が建造物調査を行い、それを受けて一部の建造物の建材の撤去を行いましたが、あれから時間が経って残された建物の損傷も進んでいます。費用の問題に加え、ユネスコ世界文化遺産に指定されていることからさまざまな制限を受け、今後の事業計画を立てづらいという問題があります。撤去するのか、保全して活用するのか、活用するならどう使うのか。ぜひみんなで考えていきたいですね」(太田さん)



その先の大文司屋を経て馬返しから再び中ノ茶屋に戻り、トレイルの振り返りを行いました。グループに分かれ、吉田口登山道で見つけた課題を洗い出し、ディスカッションを行います。
「初めて吉田口登山道にまつわるストーリーを耳にし、信仰の道、文化の道としての魅力を感じた。とはいえ、こうしたストーリーを知る人が少ないのは残念。各スポットを紹介する音声ガイドに飛べるQRコードが用意されているものの、その存在も知られていない」
「中ノ茶屋には今年からスターリンクも導入されたのだから、これを活用してデジタルコンテンツを作成できるのでは?」
「富士吉田の街と登山道を結びつける仕掛けが必要だと思う。トレイルランナーは多く見かけたので、ランナーが魅力に感じる演出を、富士吉田の街にも作るといい」
「御師町と五合目以下のつながりを楽しめる、デジタルガイドツアーのような仕掛けを作っていけないか」
「音声ガイドの存在をアピールするため、富士講とゆかりのある場所でデジタルガイドツアーを開催するのはどうだろう。都内にも富士講に関する史跡が点在するというから、それをめぐるロゲイニングイベントを行い、富士講と富士みちの認知を高めてみては?」

このように、さまざまなアイデアの交換が行われました。こうしたアイデアをもとに今後、吉田口登山道から新たな試みが生まれてくるかもしれません。開山を前に本格始動した「Mt.FUJI Re-Style Project」にご期待ください。

江戸時代にブームを巻き起こした、富士山信仰と富士講のこと
御師のいえ 大鴈丸fugaku×hitsuki
18代目・大鴈丸一志 / 奈津子
サロモンと富士吉田市が掲げるRe Style Projectでは、歴史ある吉田登山口の信仰や文化、ストーリーを再解釈し、富士山を象徴するルートである古きよき「富士みち」の魅力を改めて発信していきます。
富士みちとはなにか、どういう背景で生まれたものなのか。富士みちをひもときながらこの地に欠かせない御師(おし)の存在と、21世紀に継承される御師文化について考えていきましょう。
2ヶ月余りの開山期に、20万人もの登山者を受け入れる富士山。その登山の歴史は古く、平安時代末期にまで遡ります。とはいえ、当時、富士山を登っていたのは修験者たちに限られていました。木花開耶姫命(このはなのさくやひめのみこと)が鎮座する聖なる山で、厳しい修行に励んだといいます。この時期、末代上人は富士山に数百回も登頂し、山頂に大日寺を建立しました。
室町時代になるとこれが大衆化し、行者が庶民を連れて富士山に出かけるようになりました。それに伴い、現在の吉田口、御殿場口、須走口、富士宮口の原型となる登山道の整備が進みます。また、富士山をモチーフにした芸術作品も数多く誕生しました。人々にとって富士山とは“あの世”を意味していました。“あの世”に至ることで、一度死んで生まれ変わることができる――当時はそう信じられていたのです。

そこからさらに時代が下り、江戸時代になると富士山詣でが一大ブームを巻き起こします。きっかけは、戦国時代末期に登場した行者、長谷川角行が説いた教えでした。これが弟子の食行身禄(じきぎょうみろく)によって庶民に一気に広まり、世の中を席巻したのです。とはいえ、富士山へ出かけるためには莫大な資金が必要で、庶民にとって富士山詣では容易なことではありませんでした。一世一代の大巡礼をかなえるために生まれたのが、富士講という信仰のグループです。各講の構成員が旅行資金を積み立て、毎年、順番に参拝者を送り出すというシステムで、これができたことで多くの庶民が富士山を目指せるようになったのです。最盛期には富士講の総勢は8万人にも及んだというからも、講がどれほどの影響力をもっていたか想像できます。

富士講の信者たちが富士山を目指す際に歩いた信仰の道が「富士みち」です。大月宿(山梨県の大月)で甲州街道から分岐して富士吉田市に至る古道で、現在の国道139号線と富士吉田市の本町通りが該当します。「富士みち」が通る上吉田には、こうした富士講信者たちをサポートする御師宿坊(おししゅくぼう)が軒を連ねていました。御師(おし)とは信者たちに食事や宿を提供し、心身を清める祈祷などを授けた神職のこと。夏の登山シーズン、御師は自宅に講の信者を招いて登拝にまつわる衣食住のコーディネートを行いました。各登山口に御師宿坊が連なる御師町が築かれましたが、もっとも多くの登拝者を集めたのが上吉田の御師町でした。かつては86軒の宿坊がありましたが、富士講の衰退とともに減少し、現在も宿として機能している御師宿坊はわずか4軒のみ。そのうちのひとつが、大鴈丸の屋号をも〈御師のいえ 大鴈丸fugaku×hitsuki〉です。




御師文化を後世に伝えていく
〈御師のいえ 大鴈丸fugaku×hitsuki〉を営むのは、大鴈丸家18代目の大鴈丸一志(ひとし)さんと妻の奈津子さん。御師文化を後世に伝える拠点が必要だと感じた一志さんと奈津子さんは、1990年代に営業をやめていた実家の御師住宅をリノベして現代的なゲストハウスに蘇らせることを決意します。築453年の古民家は、一志さんの父が取り壊すことも考えていたというほど老朽化していましたが、木工職人である一志さん自身が手を入れ、現代の人々が快適に過ごせるようなしつらいにリノベーションしたのです。もちろん、宿坊らしい細工や佇まいは建物のあちこちに生かされています。エントランスを入ってすぐの板の間にはギャラリースペースを設け、古い道具や御師の斎服などかつての御師文化を垣間見ることができるオブジェを展示。家紋をあしらった美しい建具もそのまま残り、とくに海外からの旅行者に喜ばれています。



ゲストハウスを再開する以前、大鴈丸夫妻は上吉田にある御師の後継者と協働して富士講の歴史や御師文化を学ぶ勉強会を開催していました。コロナ禍により中断を余儀なくされるまで8年ほど続けていたといいます。

「御師文化や御師宿坊は廃れていく一方ですが、世間一般が思う富士山とは別の一面があること、この街のベースにはその文化があったことを現代の人にも知ってもらいたいと思っています。そうした一面を知っていただくと、『制覇する山』ではなく『生まれ変わりの山』『聖なる山』という新たな視点で富士山を感じていただけるのではないでしょうか」(一志さん)
2016年に営業を再開すると、富士山信仰に興味をもつ多くの外国人がここを拠点に富士山麓や富士吉田を散策するようになりました。
「山とつながる、自然に生かされるという日本人らしい自然観は外国人にとってとても魅力のあるものなんですね。実際、ここ2、3年で麓から富士山山頂を目指す外国人旅行者が増えているように思います。このゲストハウスでは、それを体感していただけるような宿泊体験を提供していきます」(奈津子さん)
古くて新しい富士山との向き合い方を継承すべく、大鴈丸夫妻は同世代の御師後継者たちと手を携え、新たに御師団青年部を立ち上げました。今後はインバウンド向けに御師料理(御師宿坊で行者に提供していたローカルな精進料理)をはじめとする御師文化体験ツアーの開催も予定しています。また、一志さんは新たに神職の資格を取得することも計画中。宿泊者に向けての祈祷や禊など、ここで提供してきた御師業を復活させたいと考えています。さらに、御師文化とアートを組み合わせる取り組みとして、富士山や御師文化にインスピレーションを受けた作家たちによるアーティスト・イン・レジデンスプログラムを開発したり、こうした取り組みから生まれた作品を紹介するギャラリーを開設したり……なんてことも構想しているとか。富士山が世界文化遺産に登録された理由の一つにはさまざまな芸術作品の源泉となってきた事実がありますが、御師文化が育まれた富士吉田の街に現代アートという視点がもたらされることは、富士山ルネサンスといえるかもしれません。

「信仰の歴史を垣間見られるような仕掛けがあり、どこかおごそかな気配を感じられるような、そんな魅力ある富士みち(本町通り)を再興したい」という大鴈丸夫妻。Re Style Projectは〈御師のいえ 大鴈丸fugaku×hitsuki〉をはじめとする現代の御師たちと手を携え、富士山信仰と富士みち、そして御師文化を世界に発信していきます。

【御師のいえ 大鴈丸fugaku×hitsuki】
所在地:山梨県富士吉田市上吉田7-12-16
電話番号:080-1525-9515
URL:https://www.instagram.com/fugakuxhitsuki/