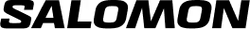江戸時代にブームを巻き起こした、富士山信仰と富士講のこと
御師のいえ 大鴈丸fugaku×hitsuki
18代目・大鴈丸一志 / 奈津子
サロモンと富士吉田市が掲げるRe Style Projectでは、歴史ある吉田登山口の信仰や文化、ストーリーを再解釈し、富士山を象徴するルートである古きよき「富士みち」の魅力を改めて発信していきます。
富士みちとはなにか、どういう背景で生まれたものなのか。富士みちをひもときながらこの地に欠かせない御師(おし)の存在と、21世紀に継承される御師文化について考えていきましょう。
2ヶ月余りの開山期に、20万人もの登山者を受け入れる富士山。その登山の歴史は古く、平安時代末期にまで遡ります。とはいえ、当時、富士山を登っていたのは修験者たちに限られていました。木花開耶姫命(このはなのさくやひめのみこと)が鎮座する聖なる山で、厳しい修行に励んだといいます。この時期、末代上人は富士山に数百回も登頂し、山頂に大日寺を建立しました。
室町時代になるとこれが大衆化し、行者が庶民を連れて富士山に出かけるようになりました。それに伴い、現在の吉田口、御殿場口、須走口、富士宮口の原型となる登山道の整備が進みます。また、富士山をモチーフにした芸術作品も数多く誕生しました。人々にとって富士山とは“あの世”を意味していました。“あの世”に至ることで、一度死んで生まれ変わることができる――当時はそう信じられていたのです。

そこからさらに時代が下り、江戸時代になると富士山詣でが一大ブームを巻き起こします。きっかけは、戦国時代末期に登場した行者、長谷川角行が説いた教えでした。これが弟子の食行身禄(じきぎょうみろく)によって庶民に一気に広まり、世の中を席巻したのです。とはいえ、富士山へ出かけるためには莫大な資金が必要で、庶民にとって富士山詣では容易なことではありませんでした。一世一代の大巡礼をかなえるために生まれたのが、富士講という信仰のグループです。各講の構成員が旅行資金を積み立て、毎年、順番に参拝者を送り出すというシステムで、これができたことで多くの庶民が富士山を目指せるようになったのです。最盛期には富士講の総勢は8万人にも及んだというからも、講がどれほどの影響力をもっていたか想像できます。

富士講の信者たちが富士山を目指す際に歩いた信仰の道が「富士みち」です。大月宿(山梨県の大月)で甲州街道から分岐して富士吉田市に至る古道で、現在の国道139号線と富士吉田市の本町通りが該当します。「富士みち」が通る上吉田には、こうした富士講信者たちをサポートする御師宿坊(おししゅくぼう)が軒を連ねていました。御師(おし)とは信者たちに食事や宿を提供し、心身を清める祈祷などを授けた神職のこと。夏の登山シーズン、御師は自宅に講の信者を招いて登拝にまつわる衣食住のコーディネートを行いました。各登山口に御師宿坊が連なる御師町が築かれましたが、もっとも多くの登拝者を集めたのが上吉田の御師町でした。かつては86軒の宿坊がありましたが、富士講の衰退とともに減少し、現在も宿として機能している御師宿坊はわずか4軒のみ。そのうちのひとつが、大鴈丸の屋号をも〈御師のいえ 大鴈丸fugaku×hitsuki〉です。




御師文化を後世に伝えていく
〈御師のいえ 大鴈丸fugaku×hitsuki〉を営むのは、大鴈丸家18代目の大鴈丸一志(ひとし)さんと妻の奈津子さん。御師文化を後世に伝える拠点が必要だと感じた一志さんと奈津子さんは、1990年代に営業をやめていた実家の御師住宅をリノベして現代的なゲストハウスに蘇らせることを決意します。築453年の古民家は、一志さんの父が取り壊すことも考えていたというほど老朽化していましたが、木工職人である一志さん自身が手を入れ、現代の人々が快適に過ごせるようなしつらいにリノベーションしたのです。もちろん、宿坊らしい細工や佇まいは建物のあちこちに生かされています。エントランスを入ってすぐの板の間にはギャラリースペースを設け、古い道具や御師の斎服などかつての御師文化を垣間見ることができるオブジェを展示。家紋をあしらった美しい建具もそのまま残り、とくに海外からの旅行者に喜ばれています。



ゲストハウスを再開する以前、大鴈丸夫妻は上吉田にある御師の後継者と協働して富士講の歴史や御師文化を学ぶ勉強会を開催していました。コロナ禍により中断を余儀なくされるまで8年ほど続けていたといいます。

「御師文化や御師宿坊は廃れていく一方ですが、世間一般が思う富士山とは別の一面があること、この街のベースにはその文化があったことを現代の人にも知ってもらいたいと思っています。そうした一面を知っていただくと、『制覇する山』ではなく『生まれ変わりの山』『聖なる山』という新たな視点で富士山を感じていただけるのではないでしょうか」(一志さん)
2016年に営業を再開すると、富士山信仰に興味をもつ多くの外国人がここを拠点に富士山麓や富士吉田を散策するようになりました。
「山とつながる、自然に生かされるという日本人らしい自然観は外国人にとってとても魅力のあるものなんですね。実際、ここ2、3年で麓から富士山山頂を目指す外国人旅行者が増えているように思います。このゲストハウスでは、それを体感していただけるような宿泊体験を提供していきます」(奈津子さん)
古くて新しい富士山との向き合い方を継承すべく、大鴈丸夫妻は同世代の御師後継者たちと手を携え、新たに御師団青年部を立ち上げました。今後はインバウンド向けに御師料理(御師宿坊で行者に提供していたローカルな精進料理)をはじめとする御師文化体験ツアーの開催も予定しています。また、一志さんは新たに神職の資格を取得することも計画中。宿泊者に向けての祈祷や禊など、ここで提供してきた御師業を復活させたいと考えています。さらに、御師文化とアートを組み合わせる取り組みとして、富士山や御師文化にインスピレーションを受けた作家たちによるアーティスト・イン・レジデンスプログラムを開発したり、こうした取り組みから生まれた作品を紹介するギャラリーを開設したり……なんてことも構想しているとか。富士山が世界文化遺産に登録された理由の一つにはさまざまな芸術作品の源泉となってきた事実がありますが、御師文化が育まれた富士吉田の街に現代アートという視点がもたらされることは、富士山ルネサンスといえるかもしれません。

「信仰の歴史を垣間見られるような仕掛けがあり、どこかおごそかな気配を感じられるような、そんな魅力ある富士みち(本町通り)を再興したい」という大鴈丸夫妻。Re Style Projectは〈御師のいえ 大鴈丸fugaku×hitsuki〉をはじめとする現代の御師たちと手を携え、富士山信仰と富士みち、そして御師文化を世界に発信していきます。

【御師のいえ 大鴈丸fugaku×hitsuki】
所在地:山梨県富士吉田市上吉田7-12-16
電話番号:080-1525-9515
URL:https://www.instagram.com/fugakuxhitsuki/