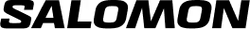中国のトレイルランニング人気の高さはよくわかっているつもりでしたが、7年ぶりに訪れてその熱さに圧倒されました。
こんにちは。トレイルランニングのウェブメディア、DogsorCaravanを運営している岩佐幸一と申します。2024年11月に中国・浙江省で開催された、中国最大規模にして最も人気が高いといわれているトレイルランニングイベントにお招きいただきました。今回は私が見た最新の中国トレイルランニング事情を前編と後編の2回にわたって紹介します。
中国最大級にして、トレイルランナーなら一度は出てみたいという「Tsaigu Trail」
訪れたのは上海の郊外にある臨海(リンハイ)という町です。現在の浙江省の南部にあたる台州(タイジョウ)という地域の中心地として古くから栄えた歴史を持ちます。この町を外敵と水害から守るために4世紀から築造された城壁をもつ町並みは「台州府城」と呼ばれ、現在では中国政府から最上級の国家観光地に指定されると同時に、重要な文化資産として保護されています。

―選手はフィニッシュまで最後の600mは台州府城の歴史的街並みの中を走る。
日本から訪れる私たちは上海の浦東国際空港から臨海に向かいます。地図上では上海のすぐ南側に位置しているように見えるのですが、実際は300km以上離れており、車での移動時間はおよそ4時間。到着した臨海は高層ビルや巨大なショッピングセンター、ネオンサインが鮮やかな飲食店が立ち並ぶ近代都市で、古い街並みの観光地を想像していた私たちを驚かせます。景観が保護されている台州府城の東側に新市街が広がっており、臨海市全体では人口が120万人に達するとのこと。中国のスケールの大きさを実感します。
臨海は中国にたくさんある地方都市の一つですが、中国国内のトレイルランニングのコミュニティの間では誰もがその名を知り、一度は走りたいと憧れる大会が開催される特別な町です。その大会の名は「Tsaigu Trail」(柴古唐斯括苍越野賽)。2015年に57kmのコースを113人が完走して始まったこの大会は、2017年にサロモンのインターナショナル・エリートアスリートが参加した頃から(ちなみにこの年の95kmの部で丹羽薫選手が優勝しています)、中国におけるトレイルランニングの人気の高まりとともに大会として大きく成長します。今年の大会には105km、50km、25kmの三つのカテゴリーのレースに合わせて14,400人の参加申し込みがあり、抽選で選ばれた3,450人が参加しました。これは中国でも有数の大会規模であり、トレイルランニングの大会では最も人気の高いものの一つなのだそうです。

―フランスから参加したサロモンアスリートのフランソワ・デンヌをはじめ、海外からのゲストを招いたレセプションが行われた。
Tsaiguが注目されるもう一つの特徴として、その競技レベルの高さが挙げられます。中国でのトレイルランニング人気の高まりとともに、各地で開催される大会は優勝選手への賞金制度を設けるようになります。この賞金が才能ある選手がプロのトレイルランニング・アスリートとなる後押しをします。Tsaiguは中国で最も充実した賞金制度を設けていることから(今年の大会で105kmの男女それぞれの優勝選手へ日本円で約86万円、約740万円の賞金を贈っています)、この大会は中国のトップ選手による頂上決戦として、そしてプロ選手を目指す若手選手の登竜門として注目されるようになりました。
しかし、賞金だけで一般ランナーも含めた大会の人気を高めることはできません。Tsaiguが人気を集める理由の一つは、台州府城の歴史的な街並みを上手く活かして選手や観衆の気持ちを高揚させ、感動へつなげる演出に力を入れていること。もう一つは、選手受付からスタート、コース誘導、エイドステーション、フィニッシュまで数多くのスタッフやボランティアによる手厚い体制でレースが運営されていることから、全ての参加選手の満足度が高いこと。詳しくは次回の後編で紹介しますが、この二つに人気の秘密があるようです。
大会会場で出会った羅光平(ロ・グァンピン)さんはIT関係の仕事をしている45歳の男性。今回が初めてのTsaiguへの参加です。「最初はマラソンをしていましたが、昨年からトレイルランニングを始めました。この大会はコースがとてもやりがいがあるし、主催者がとてもしっかりしていると仲間から聞いていたので、ぜひ走りたいと思っていました。」と話します。52歳女性の高素麗(コウ・ソリ)さんは女性のランニング仲間とTsaiguにやってきました。トレイルランニングを始めた理由を尋ねると「山が好きで、走っていると癒されます。明日の105kmはケガなく安全第一で走ります。」を笑顔で答えてくれました。
ちなみにこの大会の中国語名「柴古唐斯」(チャイクータンスー)を中国語の辞書で調べても、地図で探しても見つけることはできません。この言葉は大会が開催される台州地方の古い方言で「お前を殴る」という意味なのだそうです。この大会はガツンと殴られる覚悟で参加しなくてはいけないほど厳しいコースが待ち受けている、ということなのでしょう。それほど難しい挑戦であることも、人気の理由の一つなのかもしれません。
中国、日本、韓国のトレイルランニング・カルチャーを語り合うという新鮮な経験
サロモンはTsaiguのパートナーとして大会を支えてきましたが、今年の大会会場では「トレイルランニングのカルチャーを考える」という企画「トレイルランニング・ショー」を開催しました。中国を代表するイベントであるTsaiguをきっかけにして、アジアパシフィック諸国のトレイルランニングコミュニティを繋げようというのがその趣旨です。大会会場の目の前にあるカフェを借り、その中庭にはアジアパシフィック地域の各国のトレイルランニングの代表的なイベントや最近のトレンドを紹介する写真やパネルが展示されていました。大会に参加する選手の皆さんが無料チケットでコーヒーを楽しみながら、そこで日本をはじめとする各国のトレイルランニングについて想いをはせていました。

―「トレイルランニング・ショー」の会場ではアジア各国のトレイルランニングについての展示も。
この企画の一環として各国のトレイルランニングのカルチャーについて、事情を紹介し合いながら語り合うというトークイベント、続いて中国で人気のポッドキャストの収録が行われました。これに日本のトレイルランニングメディアとして参加してお話しするというのが、今回の私のミッションの一つでした。

―トークイベントでは聴衆を前に筆者が日本のトレイルランニングカルチャーを紹介。
中国、日本、韓国のメディアやトレイルランニングコミュニティからパネリストを集めたトークセッションには台風で大雨にもかかわらず、たくさんの方が聞きにきてくれました。話題としては、トレイルランニングにおいても、ソーシャルメディアが大会やブランド、アスリートやインフルエンサーの主要なコミュニケーションのツールになっており、意見の形成や情報の拡散に大きな役割を果たしている点は、どこも共通していました。一方、中国についての話題では中国の中央部の位置する西安で秦嶺山脈でのトレイルランニングのコミュニティで、トレイルを保護する活動や、若い世代に山を安全に楽しむための知識や経験を提供しているという経験が印象に残りました。プロ選手が人気を集めるなどトレイルランニングが過熱気味の中国において、トレイルランニングを安全に自然環境を守りながら楽しもうという訴えることは、難しいでしょうが大事なことです。一方、韓国では日本と比べて20代や女性のランナーがトレイルランニングイベントに目立つことが話題になりました。これについては、主催者が初心者が安心して参加できるコースを設定したり、パーティのような雰囲気を作って会場に来ること自体を楽しめるようにしているとのこと。韓国では女性が大会の総責任者であることも少なくないそうです。

―続くポッドキャスト収録では、さらに突っ込んだ議論が交わされた。
今回のトークイベントは決して大規模ではありませんでしたが、私にとってアジアの各国のそれぞれの事情を紹介し合うのは新鮮な経験でした。トレイルランニングに限ったことではありませんが、アジア各国はそれぞれに大きなコミュニティが存在しながらも、主流となるソーシャルメディアが各国で異なるなど、国境を越えた情報収集や交流にはハードルが付きまといます。このハードルを越えようとするサロモンの試みが、これからも続くことに期待したいと思います。

―大会前日は大雨の中、多くの皆さんがサロモンのブースを訪れていました。
次回の後編では競技レベルが高いことに加えて、演出にも力が入っているレース本番、地元の皆さんに愛され、多くのボランティアに支えられる大会で経験したおもてなしを紹介します。お楽しみに!